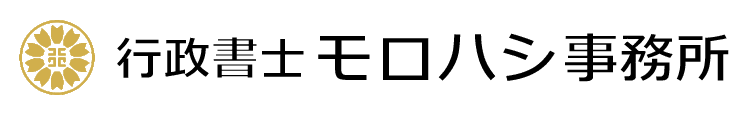目次
- 「遺言書」の有無の確認
- 相続人調査
- 相続関係説明図作成、法定相続情報一覧図の作成・申出
- 相続財産調査、相続財産目録作成
- 遺産分割協議、遺産分割協議書作成
- 名義変更等手続き
○ 預貯金・有価証券の解約・名義変更
○ 不動産の名義変更
○ 自家用車の名義変更 等 - 相続税の申告・納付
●「遺言書」の有無の確認
遺言書の有無や種類・内容によって、相続の手続きの流れが違ってきますので、先ずは、「遺言書」を確認するところからスタートすることになります。
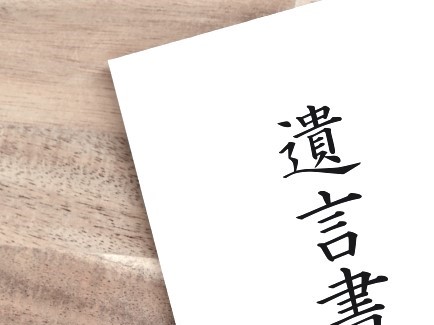
自宅等で「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」を見つけた場合
決して開封せずに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出し、「検認の申し立て」を行う必要があります(遺言書の開封は厳禁。開封した場合、5万円以下の過料が科せられます)。
検認日には、相続人や代理人の立ち合いのもと、裁判官が遺言書を開封します。あくまで、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言が有効か無効かの判断がなされるわけではありません。
申し立てから検認が終わるまで、1~2カ月ほどかかります。
*「遺言書の検認」の詳細は ↓
「遺言書の検認」(裁判所ウェブサイト)(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html)
自宅等で「公正証書遺言」を見つけた場合
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認を受ける必要はありません。
公正証書遺言では、遺言書の作成時に、遺言書の正本1通と謄本1通の交付を受けるのが通常であり、これを利用して遺言執行を行います。
自宅等で遺言書が見つからない場合
遺言が預けられていそうな機関等に問い合わせて、有無を確認することができます。
- 公正証書遺言の有無は、全国の公証役場で調べられます。原本が保管されている公証役場がどこかも分かります。
- 自筆証書遺言が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかは、法務局で確認できます。なお、遺言者が通知を希望し予め対象者を指定していた場合は、遺言書が保管されている旨のお知らせが、指定者宛てに届く仕組みになっています。
- 被相続人(故人)が生前利用していた信託銀行・貸金庫、付き合いのあった弁護士等専門家 などに預けられている可能性もあります。
●相続人調査
遺言書の確認と並行して、誰が相続人かを調査します。相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍(除籍)謄本を入手しなければなりません。
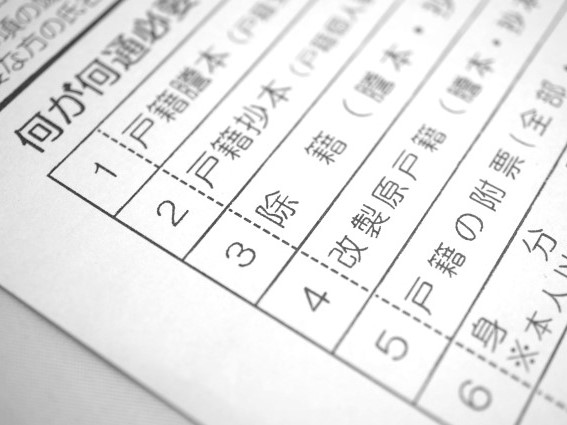
「預貯金の解約」「不動産相続登記」等々、各種相続手続きを行ううえでも、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式は必要になります。
戸籍は、婚姻や転籍、法改正等によって新しく作られるため、被相続人が生前繰り返し転籍していた場合等には、集める戸籍の量が膨大になることもあります。従前戸籍を順に遡って、各本籍地の役所から取り寄せることとなり、収集するだけで数カ月かかるケースもあります。
*「戸籍法の一部を改正する法律について」(法務省ウェブサイト)(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)を編集して記載
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書の請求ができるようになりました。
・本籍地が遠方の場合も、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※請求できる戸籍証明書等は、「本人」「配偶者」「父母・祖父母 等(直系尊属)」「子・孫 等(直系卑属)」のものです(兄弟姉妹や叔父叔母のものは不可)。
※郵送請求や、委任状による代理人請求はできません。
●相続関係説明図作成、
法定相続情報一覧図の作成・申出
戸籍一式が揃ったら、戸籍に書かれている情報に基づいて、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係性を表わした家系図のようなものです。

相続関係説明図を作成することで、被相続人と全ての相続人との関係性が分かりやすく可視化でき、各種手続きの際にも役立ちます。例えば、不動産相続登記の手続きでは、相続関係説明図を添付することで、提出した戸籍一式を手続き後に返却してもらえます(戸籍の返却が不要であれば、相続関係説明図の添付は不要)。
また、手続きが必要な金融機関等が複数カ所になる場合には、「法定相続情報証明制度」を利用すると便利です。この制度を利用すると、1セット分の戸籍一式を使い回したり、同じ戸籍を何セット分も取得したりする必要がなくなり、手続きにかかる時間や戸籍取得にかかる費用を節約することができます。
*「法定相続情報制度」の詳細は ↓
「法定相続情報制度について」(法務局ホームページ)(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)
●相続財産調査、相続財産目録作成
相続発生時に故人が有していた全ての財産(プラスの財産、マイナスの財産)が相続財産となります。相続放棄をするには「相続の開始を知った日から3カ月以内」という期限もあるため、速やかに調査を始め、相続財産の洗い出しを行います。

様々な資料を手掛かりに、相続財産を調査します。後になって、新たに財産が見つかった場合、遺産分割協議や相続税申告のやり直しをしなければならなくなるため、入念に調べる必要があります。
被相続人の財産を把握するための資料としては、例えば、納税に関する書類等、預貯金通帳、金銭消費貸借契約書・財産贈与契約書等、証券会社や保険会社等から届いた案内書等が考えられます。
なお、通帳等が見つからない場合でも、銀行等に対し、被相続人の取引が有ったかどうか照会をすることは可能です。また、ネット銀行・ネット証券口座等、デジタル形式での保有財産(デジタル遺産)についても、「口座状況照会」や「相続財産開示」の請求により確認を行うことができます。
相続財産を洗い出したら、「財産目録」を作成します。「財産目録」とは、被相続人の全ての財産(プラスの財産、マイナスの財産)を一覧表に整理して記載したものです。財産目録により、遺産の全容を確認することができ、遺産分割協議の際にも活用できます。
●遺産分割協議、遺産分割協議書作成
遺言書が無い場合、誰がどの財産をいくら相続するかを決定するため、法定相続人全員による話し合いが必要となります(遺産分割協議)。
(法的にも内容的にも問題の無い遺言書が遺されていた場合には、その遺言書の内容が優先されることになります。⇒ 参照:「遺言書に関する基礎知識」ページ )
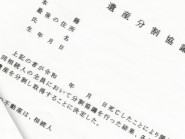
法定相続人全員で協議し、全員が合意した内容で、遺産を分けることになります。法定相続人全員が納得すれば、必ずしも法定の相続分(割合)で分ける必要はありません。
遺産分割協議で相続人全員が合意に至ったら、その内容に基づいて「遺産分割協議書」を作成します。銀行解約や不動産名義変更等、遺産分割協議書を提出しないとできない手続きもあります(遺産分割協議書の内容に不備があると、各種手続きの際に利用できないものとなってしまうことがあります。)
遺産分割協議書には、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかを具体的に明記し、完成した書面内容を確認したうえで相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。
なお、遺産分割協議は、相続発生後いつ行っても良いものの、相続税の申告と納税については、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日)の翌日から10カ月以内に行わなければならず、分割協議が成立していない場合でも相続税の申告期限が延びることはないため注意が必要です。
●名義変更等手続き
○ 預貯金・有価証券の解約・名義変更
遺言書や遺産分割協議により、預貯金・有価証券の分割方法が決まったら、各金融機関で手続きを進めます。各金融機関所定の手続用紙を入手し記入のうえ、必要書類(戸籍一式、印鑑証明等)を揃えて提出します。戸籍一式の還付を希望する場合は、提出時に申し出ます。
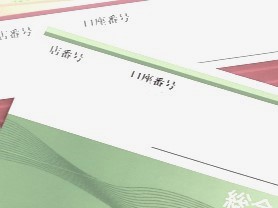
なお、有価証券の相続では、基本的には、口座の解約(被相続人名義のまま売却)ができないため、相続する人は、被相続人の証券口座がある金融機関に自身の証券口座を開設し、被相続人の財産を移管して名義変更を行う必要があります(被相続人と同じ金融機関に自身の証券口座がもともとある場合には新たな開設は不要)。
○ 不動産の名義変更
土地や建物など、不動産を相続した場合には、取得した相続人への名義変更を行います。
(法的にも内容的にも問題の無い遺言書が遺されていた場合には、その遺言書のとおりに執行されることになります。)

相続した不動産を売却する予定でも、一旦は相続人の名義に変更しなければなりません。
なお、相続等により「農地」や「森林の土地」を新たに取得した場合には、それぞれ、農業委員会、市町村長への届出も必要です(農地法3条届出、森林の土地の所有者届出)。
*「相続登記の申請義務化特設ページ」(法務省ウェブサイト)(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html)を編集して記載
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
※令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産については、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をすれば問題ありません。
*「相続土地国庫帰属制度について」(法務省ウェブサイト)(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)を編集して記載
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が、開始しました。
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことを可能とする制度です。
制度のポイントは、以下のとおりです。
(1)相続等によって、土地の所有権または共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(2)法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
(3)法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
(4)土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
○ 自家用車の名義変更
被相続人が車検証上の所有者であった場合には、自動車の相続の手続きが必要です。
普通自動車と軽自動車では、手続きが異なります。

普通自動車は、相続人(新所有者)が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は、相続人(新所有者)が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で、手続きを行います。
* 運輸支局等の詳細は ↓
「全国運輸支局等のご案内」(国土交通省ホームページ)(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html)
* 軽自動車検査協会の詳細は ↓
「全国の事務所・支所一覧」(軽自動車検査協会Webサイト)
(https://www.keikenkyo.or.jp/office/?cl=on&vmid=674)
●相続税の申告・納付
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額(『3,000万円+(600万円×法定相続人の数)』の算式で計算)を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。
電話でのご予約

受付時間:平日 10時~18時30分
※来客時等、電話がつながらない場合があります。ご了承ください。
※番号通知設定にておかけいただき、留守番電話にご用件をお話ください。内容を確認次第、折り返しいたします。
メールでのご予約

メールフォームから
お問い合わせください。
※お問い合わせの内容を確認後、3営業日以内に折り返し電話連絡をさせていただきます。