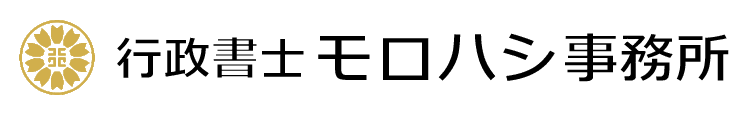目次
- 成年後見制度の概略
○ 法定後見制度
○ 任意後見制度 - 任意後見を補う仕組み
○ 見守り契約
○ 財産管理等委任契約(生前事務委任契約)
○ 死後事務委任契約
●成年後見制度の概略
認知症等の理由で判断能力の不十分な人に対して、援助者(必要な事務の代理を行う人)を付け、財産を管理したり、契約を締結したりといった本人が自分独りですることが難しい手続きを代わりに行うこと等によって、本人を法的に保護・支援するのが、成年後見制度です。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度に大別されます。

○ 法定後見制度
何も対策をしないまま判断能力が低下した場合に、後見人等を付けるには、家庭裁判所に選んでもらうしかありません。
すでに判断能力が衰えた人のために、申立権者(本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長等)が、後見等(本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度有)の開始を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任します。成年後見人等を監督する成年後見監督人等が選ばれることもあります。
成年後見人等の権限は、基本的に法律で定められており、「後見」「保佐」「補助」の類型に応じて、一定の範囲内で、代理したり、本人が締結した契約を取り消したりすることができます。
なお、後見等の開始の申立てにおいて、希望の成年後見人等候補者(親族等特定の人)を申し出ていたとしても、希望通りの人が選任されるとは限りません。また、そのことを理由に後見開始等の審判に対して不服申立てをすることはできません。
※成年後見人等が選任されると、家庭裁判所から東京法務局へ届出(嘱託)がされ、登記されます。
○ 任意後見制度
判断能力の低下に備えて、判断能力があるうちに対策をしておけば、親族等自分の信頼する人を後見人にすることができます。
予め自分の後見人になる人(任意後見受任者)を選び、将来、判断能力が不十分な状況となった場合に、本人の決めた人(任意後見人)から後見事務を行ってもらうという契約(任意後見契約)を締結しておきます。任意後見人に委任する事務の内容についても、法律の趣旨に反しない限り自由に、任意後見契約で決めておくことができます。任意後見契約は、本人が十分な判断能力を有するときに、公正証書により締結しておく必要があります。
なお、任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力を生じるため、任意後見受任者は、任意後見監督人が選任されるまでは、任意後見契約で委任された事務を行うことはできません。
また、任意後見契約の発効後、任意後見人は、任意後見契約で定めた範囲内で本人を代理することができますが、本人が締結した契約を取り消すことはできません(法定後見にあるような、本人の行為に対する取消権はありません)。
【任意後見契約の締結から発効までの流れ】
- 本人に契約の締結に必要な十分な判断能力があるときに
本人(委任者)と後見人になってくれる人(任意後見受任者)との間で、『将来、本人の判断能力が不十分な状況となった場合に、任意後見人に代理権を与える』という内容の契約(任意後見契約)を締結します。この契約は公正証書により締結する必要があります。任意後見契約がされると、公証人から東京法務局へ届出(嘱託)がされ、登記されます。
※任意後見監督人が選任されていない現段階では、任意後見契約の効力は生じていないため、「任意後見受任者」は、まだ「任意後見人」ではありません。
*「登記事項証明書」の見本 ↓
「登記事項証明書【任意後見契約】(任意後見監督人が選任される前の場合)」[PDF](東京法務局ホームページ)(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/000128568.pdf)
- 本人の判断能力が低下したときに
申立権者(本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる人)が、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が、任意後見監督人を選任します。任意後見監督人が選任されると、家庭裁判所から東京法務局へ届出(嘱託)がされ、登記されます。登記が完了すると、裁判所から任意後見人及び任意後見監督人に通知書が送付されます。
- 任意後見の開始
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者が任意後見人となり、任意後見契約で委任された事務を開始します。任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約の内容どおりに適正に仕事をしているかを監督します。
金融機関取引等の手続きの際には、任意後見人としての身分や代理権の内容等を証明する「登記事項証明書」が必要です。この「登記事項証明書」は、任意後見人等限られた人からの請求により発行されます。
*「登記事項証明書」の見本 ↓
「登記事項証明書【任意後見契約】(任意後見監督人が選任された後の場合)」[PDF](東京法務局ホームページ)(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/000128569.pdf)
●任意後見を補う仕組み
任意後見契約の効力は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから生じ、また、本人の死亡によって消滅します。
そのため、任意後見契約を締結してから効力が生じるまでの期間の財産管理や、本人死亡後の事務処理については、任意後見契約では対応ができません。
「見守り契約」「財産管理委任契約(生前事務委任契約)」「死後事務委任契約」を組み合わせて利用することで、任意後見契約では対応できない部分を補うことができます。

○ 見守り契約
任意後見契約の効力が発生するまでの間に、支援者(受任者)が定期的な訪問や連絡を行うことによって、本人(委任者)の判断能力の低下や生活状況の変化等を確認し、任意後見を開始させる適切な時期を判断するための契約です。
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約に移行します(見守り契約は終了します)。
○ 財産管理等委任契約(生前事務委任契約)
判断能力はしっかりしていても、寝たきりや車いす生活で移動が困難になったり、目や手が不自由で文字が書けない等の理由により、金融機関や行政機関での手続き等を自分で行えなくなる場合があります。このような場合に、親族や信頼できる人に代理権を与え、財産管理や身上看護等に関する事務を委任する契約です。
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約に移行します(財産管理委任契約は終了します)。
○ 死後事務委任契約
本人が亡くなった後の各種手続き等に関する事務を、第三者(個人、法人)に委任する契約です。
本人が亡くなると、任意後見契約が終了し、死後事務委任契約に移行します。
本人の死亡後に行う事務には、以下のようなものがあります。
・葬儀、納骨、永代供養等に関する事務
・未払い費用等の支払に関する事務
・行政官庁等への届出に関する事務
・住居の整理に関する事務
・相続人・遺言執行者等への財産の引渡に関する事務
・相続財産管理人の選任申立手続に関する事務 等
電話でのご予約

受付時間:平日 10時~18時30分
※来客時等、電話がつながらない場合があります。ご了承ください。
※番号通知設定にておかけいただき、留守番電話にご用件をお話ください。内容を確認次第、折り返しいたします。
メールでのご予約

メールフォームから
お問い合わせください。
※お問い合わせの内容を確認後、3営業日以内に折り返し電話連絡をさせていただきます。