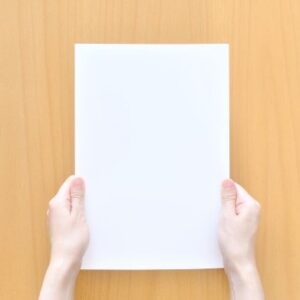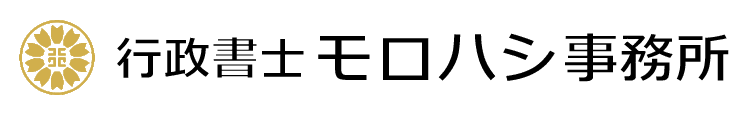法的に効力のある遺言書にするためには、
民法で定められた方式に従って作成しなければなりません。
誤った書き方では、せっかく記された遺志が実現できなかったり、
かえって揉め事の火種となってしまう可能性もあります。
また、遺言書に書いても、法的に「できないこと」もあります。
遺言書の作成をお考えのかたへ

当事務所では、お客様の作成する遺言書が
法律の規定に従ったものとなるよう、
サポートを行っております。
サークル等各種コミュニティ様向けの、
出前講習会も承っております。
お任せいただける業務の詳細
- 公正証書遺言作成サポート
手続きに必要な戸籍等書類の収集、遺言書本文の起案、公証人との打ち合わせ、証人の手配 等、総合的にサポートいたします。付言事項(遺言の内容をどのような気持ちで決めたのか等、思いをつづることができる)の原案作成も行います。 - 尊厳死宣言公正証書作成サポート
遺言と一緒に、尊厳死宣言(自らの考えで尊厳死を望む(延命措置を望まない)旨を宣言するもの)の公正証書を作成される方も増えています。ご希望がある場合には、手続きのサポートをさせていただきます。 - 任意後見契約書作成サポート
(任意後見契約、見守り契約、財産管理等委任契約(生前事務委任契約)、死後事務委任契約)
⇒ 詳細はコチラ - 自筆証書遺言相談・起案サポート
遺言の基本的なルールの説明、ご意向に沿った遺言書にするためのポイントの案内、遺言書本文の起案 等をいたします。 - エンディングノート作成支援
エンディングノートの作成に取り組むためのお手伝いをさせていただきます。エンディングノートは、葬儀やお墓に関する希望、資産、万一のときの連絡先等の情報を記入しておくノートです。また、ご自身の生い立ちや経歴等を整理し、人生を振り返ることもできます。遺言書作成前の準備としても役立ちます。 - コミュニティ向け 出前講習会
遺言書やエンディングノートについて、分かりやすくお話しいたします。質問タイムあり。
もしもへの備えの第一歩として、コミュニティの皆様と一緒に知識を共有しませんか。
料金のご案内
標準的な事案の場合の、目安料金を表示しています。参考値としてご覧ください。事案内容により、報酬・手数料実費等はそれぞれ異なります。
お客様のご相談内容をお聞きしたうえで、個別事案に応じたお見積書を提示させていただきます。お見積書をご確認のうえ、ご依頼をご検討いただければと思います。

ご相談から業務完了までの流れ
(公正証書遺言作成サポートの場合)
公正証書遺言書の作成について、当事務所にご相談・ご依頼いただく場合の基本的な流れは、以下のとおりです。ご参考にご覧ください。
その他作成サポート業務(尊厳死宣言公正証書、自筆証書遺言、エンディングノート等)の流れについては、お問い合わせください。
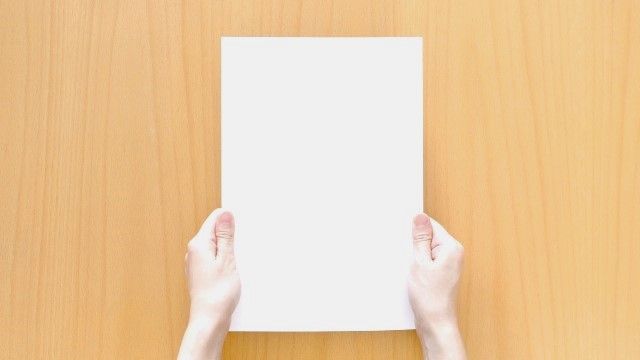
- まずは、お電話またはメールにてお問い合わせいただき、ご相談日のご予約をお願いいたします。
※事前のご予約により、休業日や営業時間外のご相談もお受けしております。
※お客様のご自宅・ご指定場所等、ご都合に合わせて面談場所を設定することも可能です。(別途 交通費・日当(出張料)が発生する場合があります。⇒ 「交通費・日当(出張料)」はコチラ - ご相談時の参考資料としてご準備いただきたい書類等を、予約日程調整の際にご案内させていただきます。
- ご予約いただいた日時に、直接お会いして、ご相談内容の詳細をお伺いいたします。
- ご相談内容をお聞きしたうえで、お客様の個別事案に応じた業務内容のご提案及びお見積書のご提示をさせていただきます。
- 業務提案やお見積の内容にご納得いただき、お申込みとなりましたら、委任契約を締結いたします。
※必要書類に、ご署名・ご捺印をいただきます。
※手続きに必要な資料等をお預かりさせていただきます。
※その他 ご準備いただく書類等をご案内いたします。 - 委任契約書を交わしたうえで、内金20,000円を申し受けます。ご入金を確認次第、業務に着手させていただきます。
- 直接ご本人と面談し、誰に何を相続させたいかといったご希望や、ご心配事等についての、聞き取りを行います。
- お客様からお伺いした内容に基づき、どのような事項を書く必要があるか具体的に検討・整理していきます。予備条項や付言事項の要否の確認もさせていただきます。
●遺言本文の起案、付言事項の原案の作成
- ヒアリングの内容に基づき、法的に正確な遺言本文の文案を作成いたします。
- 付言事項のご希望がある場合には、その原案も作成いたします。
- 文案の準備が整い次第、ご本人に内容をご確認いただきます。加筆修正点があれば調整を行います。
●必要書類の収集
- 推定相続人を特定するための戸籍謄本等を収集いたします。
- 財産に不動産がある場合は、固定資産税評価額を確認するための書類が必要になります。公図や不動産登記の情報の取得が必要な場合もあります。
●公証人との打ち合わせ、証人の手配
- 作成した遺言書原案や、戸籍等必要書類一式を公証人に提示し、事前打ち合わせを行います。
- 公正証書遺言の作成の際に立ち会う証人(2名、当事務所行政書士を含)を手配いたします。
- 遺言者、公証人、証人の都合の調整を行い、公正証書遺言の作成日を確定します。
※公正証書遺言の作成日当日に、公正証書作成の手数料(公証役場の手続き費用) 及び 当事務所の請求額(報酬・各種費用実費等)をお支払いいただきます。作成日確定の連絡の際に、金額のご案内をいたします。
※公証役場、あるいは遺言者のご自宅や病院等にて行います。
※公証人に出張してもらい、公証役場以外の場所にて行う場合は、作成手数料加算、公証人の交通費及び日当が発生します。
- 公証人から公正証書の内容が読み上げられ、内容に間違いがないかを確認した後、遺言者、証人が署名捺印を行います。
- 最後に公証人の署名捺印が行われ、公正証書遺言が完成します。
- 公正証書遺言の「正本」及び「謄本」が交付されます。
※当事務所が遺言執行者に指定されている場合は、当事務所にて「正本」をお預かりさせていただきます。
※「原本」は公証役場で保管されます。
- 公正証書遺言の「正本」及び「謄本」が交付されます(「原本」は公証役場で保管されます)。
※当事務所が遺言執行者に指定されている場合は、当事務所にて「正本」をお預かりさせていただきます。 - 公正証書作成の手数料(公証役場の手続き費用)、当事務所の請求額(報酬・各種費用実費等)をお支払いいただきます。
- 業務終了後、万が一、お困り事やご不明点等がでてきた場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。
- 当事務所が遺言執行者に指定されているお客様へは、1年に1回程度の定期的な連絡を行い、ご様子を伺わせていただきます。
電話でのご予約

受付時間:平日 10時~18時30分
※来客時等、電話がつながらない場合があります。ご了承ください。
※番号通知設定にておかけいただき、留守番電話にご用件をお話ください。内容を確認次第、折り返しいたします。
メールでのご予約

メールフォームから
お問い合わせください。
※お問い合わせの内容を確認後、3営業日以内に折り返し電話連絡をさせていただきます。